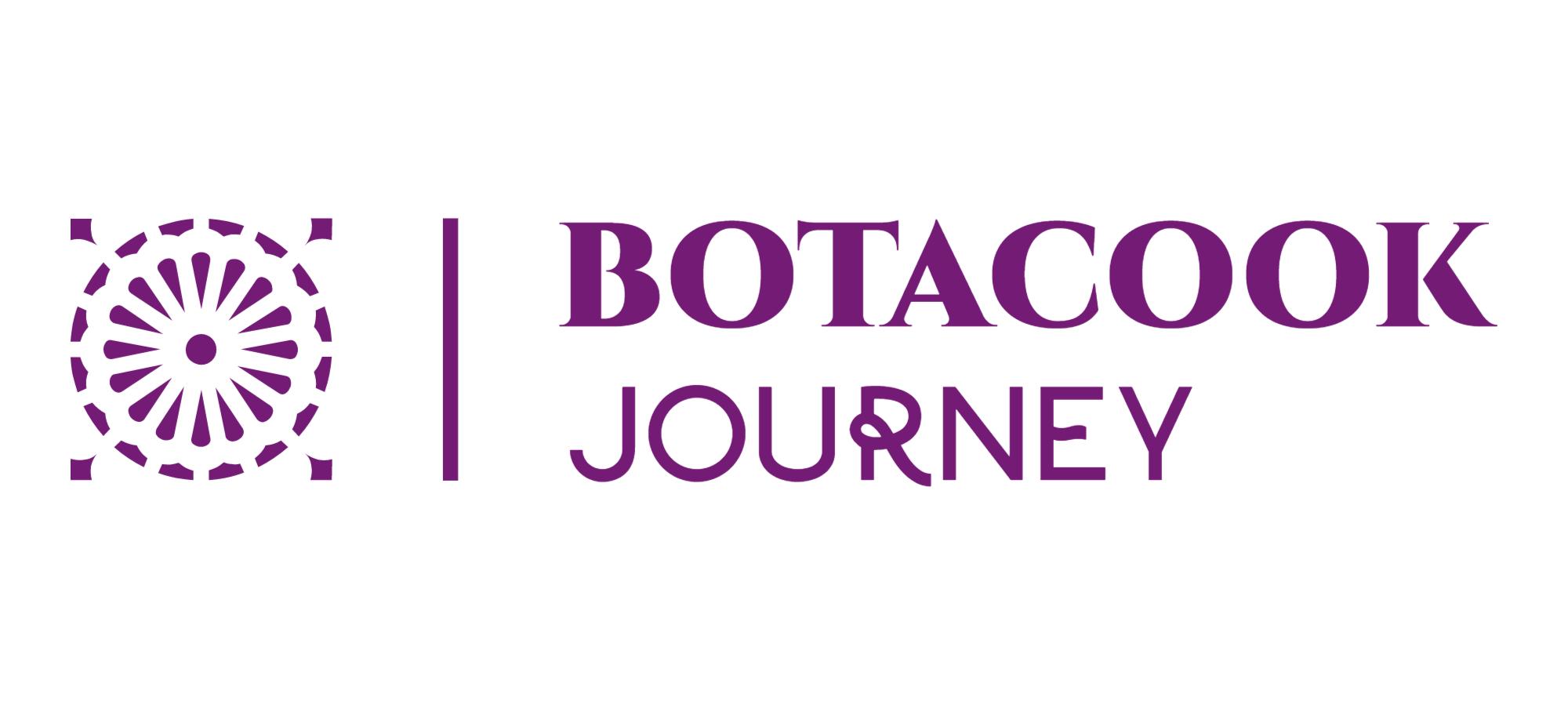冬の寒い時期に車で走っているとよく目にするのが「イチゴ狩り」の看板やのぼりです。道路沿いに次々と現れるイチゴ農園の入り口付近では、お揃いの衣装を着た人たちが、やって来る車に向かってしきりに呼び込みをしています。たいていは一定時間でハウス内のイチゴを食べ放題にしていて、練乳やコンデンスミルクを配ってくれるところもあり、特に子供連れの観光客に人気が高いようです。こういったイチゴの観光農園の開園期間はだいたい12月中旬から5月上旬に設定されています。お店にもたくさん並べられるのは冬場で、ゴールデンウィークごろになるともう季節は終わりというイメージ。実はイチゴの旬というのはもともと4~5月です。それが、クリスマスケーキ需要によってイチゴの大量消費シーズンとなった12月下旬に出荷が間に合うよう、促成栽培が定着しました。本来は秋に気温が下がると花芽分化[1]新しく出る芽が花の咲く芽になることがおこり、翌春になって気温が上がるにつれ開花し結実します。でも、そのまま秋に苗を植え付けて、暖かいハウス内で栽培することで12月には収穫ができるようにしているのです。最近は世界的な気候変動の影響もあり、秋の気温も高くなってきました。そのため、花芽分化が遅れて出荷時期に間に合わないこともあるようで、低温処理技術などを加えた栽培方法が研究されています。

イチゴはバラ科の多年草です。草本類なので野菜に分類されることがあるものの、甘みもあり、その用途からも果物として位置付けるほうがいいでしょう。店頭に並ぶイチゴには「あまおう」、「とちおとめ」といった有名品種をはじめとして多々ありますが、ほとんどすべてがオランダイチゴ属の栽培品種とされます。その名の通り、日本には江戸時代の終わりにオランダから伝えられたものです。当時は観賞用で、食用にされるのは、さまざまな品種と交配がおこなわれるようになった明治以降だとききました。英語ではstrawberryまたはgarden strawberry と呼ばれるものがこれにあたり、学名はFragaria ananassaといいます。イチゴの食用となる赤い部分は、実は果実ではありません。果実は表面にたくさん付いているゴマのような粒々です。硬い果皮に包まれているため種子にも見えますが、痩果(そうか)と呼ばれる果実のタイプで、タンポポなどのキク科やキンポウゲ科の植物にも見られます。食用部分は花托(かたく)[2]花床(かしょう)とも言いますという、花弁やおしべ、めしべ、萼などが付いている部分。つまり本来は花を支える場所で、茎の先端が分厚くなったものです。このように果実でない箇所が果実状になることを偽果と呼びます。同じバラ科のリンゴやナシの食用部分も、花托が変化して大きくなる偽果です。

世界で生産されるイチゴは年間に1,000万トン近くになるそうです。そのうちの40%が中国によります。ヨーロッパでは、スペイン、ポーランド、イタリア、ドイツが4大生産国です。スペインではマドリード近郊のアランフェスAranjuez[3]世界遺産に登録された王宮とアランフェス協奏曲が有名がイチゴ産地として知られていて、マドリード~アランフェス間を走るTren de la Fresaトラン・デ・ラ・フレサ=イチゴ列車なる観光列車があります。