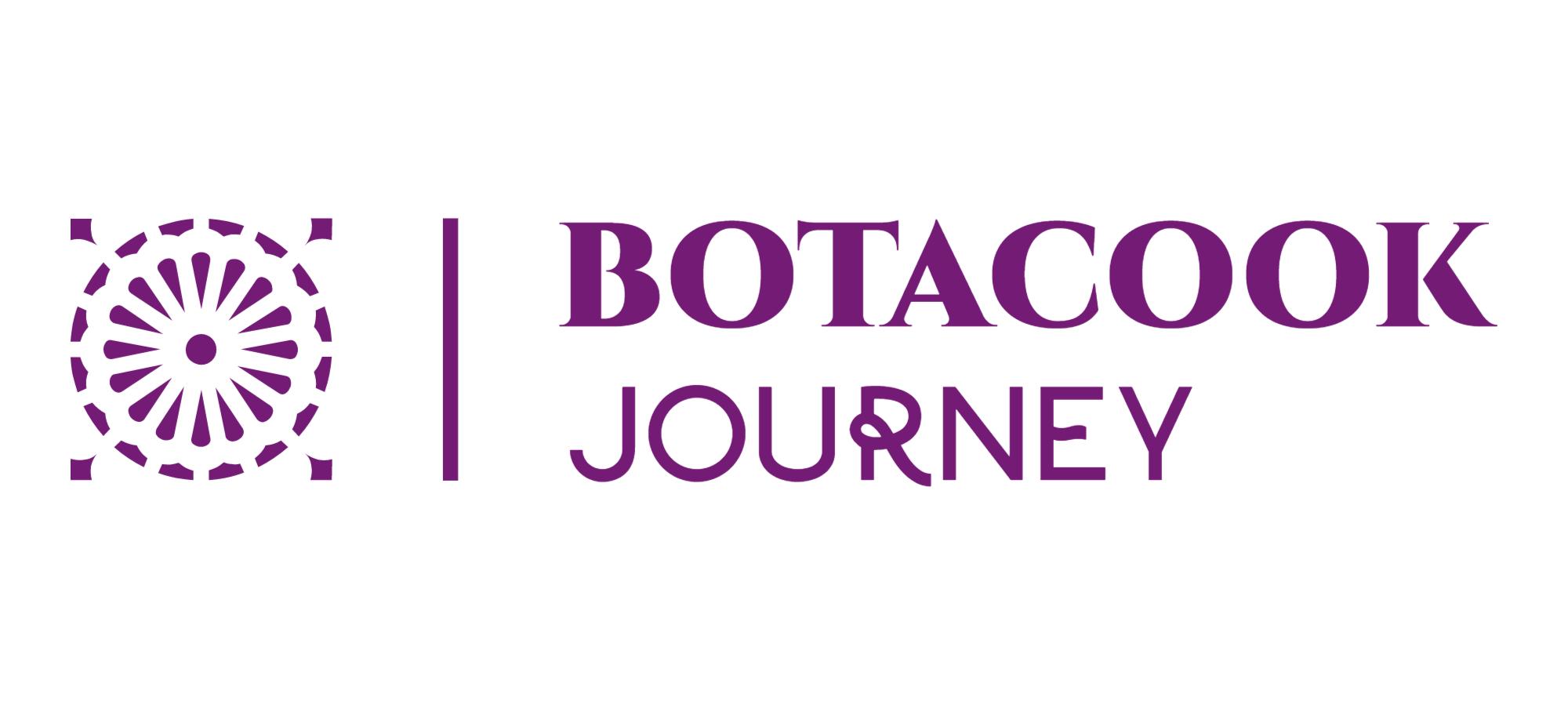世界で最も古い栽培果樹といわれるのがイチジクFicus caricaです。原産地は現在のイエメン[1]アラビア半島南西部あたりで、古代のメソポタミアでは幅広く生産がおこなわれていました。その後東地中海や中央アジア方面、さらに西ヨーロッパや中国へと伝播していきます。現在もエジプト、イラン、トルコなど原産地に比較的近い温暖な乾燥地域が主要な生産国です。
日本への伝来について、熊本県天草市のウェブサイトを見ると、《16世紀に、天正遣欧少年使節団を引率したメスキータ神父の手紙には、「ポルトガルからイチジクの苗を持ってきた」と書かれており、天草はイチジクの発祥の地と言われ、昔から”南蛮柿”と呼ばれ親しまれてきました。》とあります。使節団が帰国したのは1590年[2]秀吉の天下統一の年で、メスキータとは通訳として随行したイエズス会の神父です。

イチジクの名は聖書の中にも何度となく登場し、古代から人々にとって重要な植物であったことがわかります。有名なのは、アダムとエバがヘビにそそのかされて、神から取って食べてはいけないといわれた善悪を知る木の実を食べるという創世記の記述でしょう。彼らは目が開け、自分たちが裸であることを知って、イチジクの葉をつづり合わせて腰に巻いたという楽園追放へつながるお話です。[3]創世記第3章2~7節このことから、英語ではイチジクの葉fig leafというと覆い隠すものを意味します。
古代ローマでは、共和制から帝政への転換の重要な要因となるポエニ戦争が起こりました。前後3回にわたるカルタゴ[4]現在のチュニジアを中心に北アフリカからヨーロッパの地中海沿岸で栄えた国家との戦争を指します。ポエニとはカルタゴの人々のことで、もともと現在のレバノン辺りを拠点とした海の民フェニキア人に対するローマでの呼称です。第二次ポエニ戦争時[5]紀元前219~201年 ハンニバル戦争とも呼ばれますに要職にあった大カトー[6]マルクス・ポリキウス・カトー、小カトーは曾孫、検閲官カトーとも呼ばれるがカルタゴ殲滅を熱望し、元老院に強く働きかけました。彼は大きくて新鮮なイチジクをカルタゴの象徴として持ち出します。それには、立派な果実を収穫する豊かさと、日持ちのしないイチジクが瑞々しいまま届けられるほど近くにある脅威として示す、という意味がありました。結局、カルタゴはその後の第三次ポエニ戦争[7]紀元前149~146年で滅亡します。

イチジクはクワ科の落葉高木です。イチジク属として世界に600種以上が確認されています。共通するのは葉や果肉から白い乳液を出すことです。イチジクは、その乳液が胃腸の働きを助けるとされ、古くから生薬として利用されてきました。樹皮は白っぽくザラザラしており、その葉は20~30cmと大ぶりで、3~5片に分かれて深い切れ込みが入ります。特徴的なのは花です。無花果という漢字名のとおり一見花が咲かずにいきなり実がなるように思われます。実際は花托[8]花びらやめしべ、おしべが付く部分の部分が発達して先が膨らんだ卵型の花序となり、その内側に小さな花が密生するのです。それが受粉することでそのまま果実へと変化していきます。日本で栽培されているイチジクは自花受粉が可能です。しかし、イチジク属は本来雌雄異株で、その受粉にはイチジクコバチ科の体長1~2mmの小さなハチが媒介します。このハチが内部に寄生し産卵、成虫となったハチが他の株へ移動することで結実につながるわけです。
台湾のデザートとして知られている愛玉子(オーギョーチー)は、日本にも自生しているつる性イチジク属のオオイタビの仲間で、カンテンイタビという植物からつくります。種子を水の中で揉むと多量に含まれるペクチンが溶け出して、常温でも固まるのが特徴です。