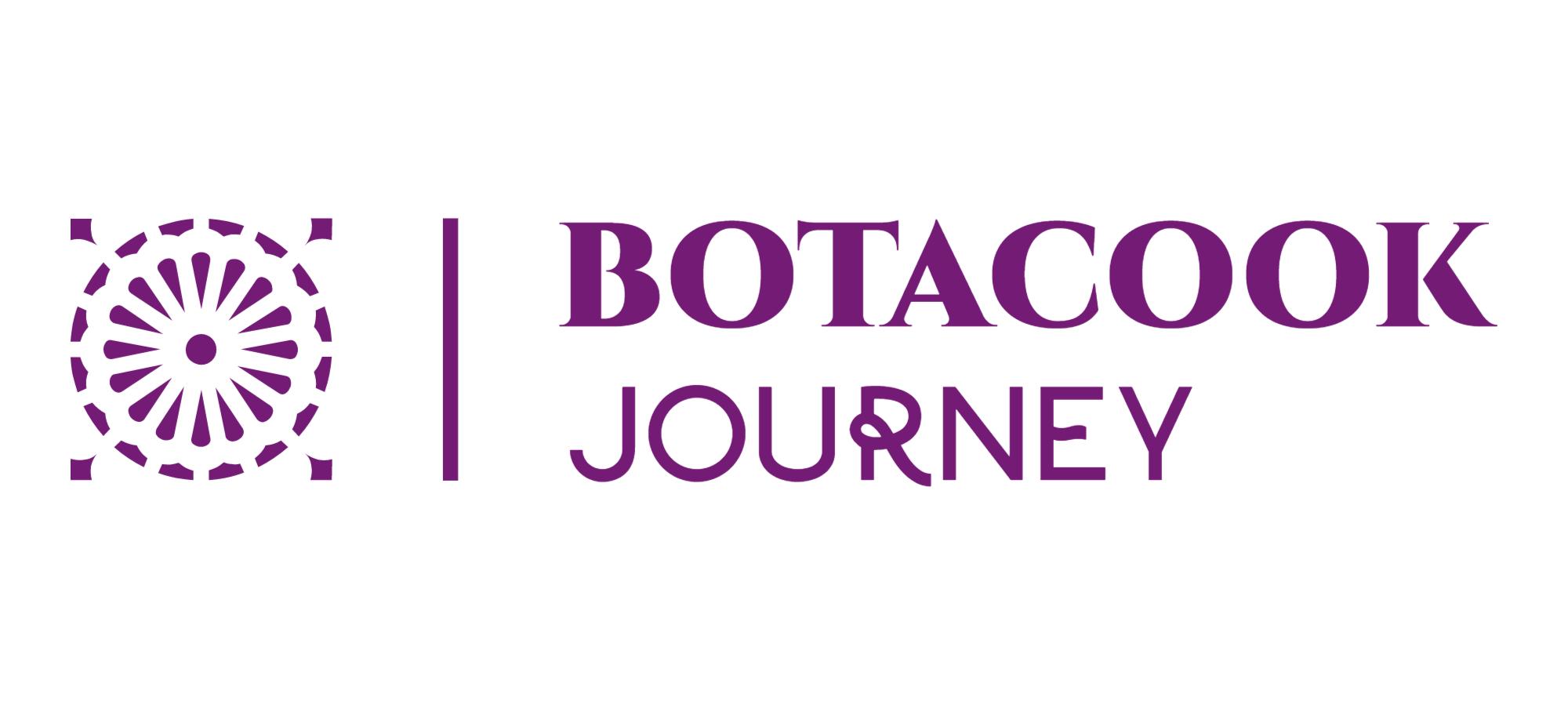小学生のころ、テレビではじめてオランダ代表のサッカーの試合を見ました。そのときに、選手たちがオレンジ色のユニフォームを着ていたので、「オランダ」と「オレンジ」は語源的に関連があるのだと勝手に思い込んだのです。もちろん、綴りを見ればHolland とorangeに直接関係がないということぐらいはすぐにわかります。でも、当時の小学生はそんなことまで考えるわけもありませんでした。
「オランダ」という日本語の国名は、オランダ独立の中心となったホラント州の名前が国の俗称として使われるようになっていたことに由来します。正しい国名はオランダ語で「低地の王国」を意味するKoninkrijk der Nederlandenコーニンクレイク・デア・ネーデルランデン(英語:Kingdom of the Netherlands)といいます。オランダ語ではネーデルランデンのアクセントは最初の「ネ」のところにあり、普通はオランダ単独でネーデルラントNederlandと呼びますが、正式には海外領土を含むためlandの複数形landenになっています。英語名は低地という普通名詞なので冠詞が付くのです。実際にオランダ人が発音するとネールラントと聞こえます。

現在のオランダ王家はオラニエ・ナッサウ家といいます。もともとは16世紀、ハプスブルク家の領土であったネーデルラントと現在の南仏のオランジュ公国を相続したオラニエ公ヴィレム1世Willem I(在位1544-1584年)からはじまりました。日本の西洋史の教科書ではオレンジ公ウィリアムという名前になっていることが多いかもしれません。オラニエはオランジュのオランダ語読みです。オランジュ公国のもととなるオランジュOrangeの町の歴史は古代ローマに遡り、当時はケルトの水神の名からアラウシオArausioと呼ばれていました。その名が少しずつ変化してオランジュになったといわれます。ヴィレムの時代にはすでに植物のオレンジはヨーロッパで流通していて、その果実の色から付けられたオレンジ色も知られていました。ヴィレムは公国の名と同じオレンジ色を入れたオレンジ・白・青の三色旗を公国の旗として使用しており、それがそのまま後のネーデルラント(オランダ)の国旗に制定されたのです。しかし、1795年にフランス革命軍に占領されてバタヴィア共和国(~1806年)となったオランダでは、オラニエ家の旗の使用は禁止。フランスと同じ赤・白・青の三色旗に変更されました。そのためオランダ王家と国民は、国旗とは別にオレンジ色を自分たちの色として大事にしてきたのです。現在もサッカーだけでなく、あらゆる機会にオレンジのアイテムは使用され、国王誕生日には国中がオレンジ色に染まります。

オレンジの色はオランダ人が入植した地でも継承されます。代表格は、オランダ人が最初の入植地として基礎を築き、ニーウ・アムステルダムNieuw Amsterdamの名で呼ばれていたニューヨーク。ここを本拠にするMLB[1]メジャーリーグ・ベースボールのメッツやNBA[2]ナショナル・バスケットボール・アソシエイションのニッカーボッカーズ(ニックス)、NHL[3]ナショナル・ホッケー・リーグのアイランダーズなどはオレンジがチームカラーです。メッツの場合は、かつて1958年にニューヨークからサンフランシスコへ移転したジャイアンツのチームカラーだったオレンジと、ロサンジェルスへ移ったドジャーズの青を引き継いでいます。

フランス南部のプロヴァンス地方にあるオランジュの町は、教皇庁で有名なアヴィニョンの北20㎞ほどに位置します。保存状態の良いローマ時代の遺跡群が世界遺産に登録されている有名な観光地です。その遺跡の中でも特に素晴らしいのが1世紀に建造された古代劇場Théâtre antique。斜面を利用した客席の上にある公園には、かつてのオランダ女王ユリアナが植樹したというナラの木があります。

植物のオレンジは、中国南部やインド北東部辺りが原産といわれ、それがペルシャやアラビアを通じてヨーロッパにもたらされました。原産地では「ナランガ」と呼ばれていたようですが、それが変化して各地の名前に定着したのでしょう。スペイン語ではナランハnranja、ポルトガル語ではラランジャlaranja、イタリア語ではアランチャaranciaといった具合です。面白いのは、肝心のオランダでは、オレンジのことをシナーサッペルsinaasappelといいます。「中国のリンゴ」を意味しますが、ロシア語でもアーペルシンапельсин、スウェーデン語でもアペルシンapelsinと同じ意味の言葉です。さらにギリシャ語ではポルトカリΠορτοκάλι、トルコ語はポルタカルportakal、ルーマニア語はポルトカーレportocaleといいます。これはポルトガル人がオレンジを紹介したからに違いありません。名称の相違からオレンジの伝わった経路がわかるようで興味深いです。