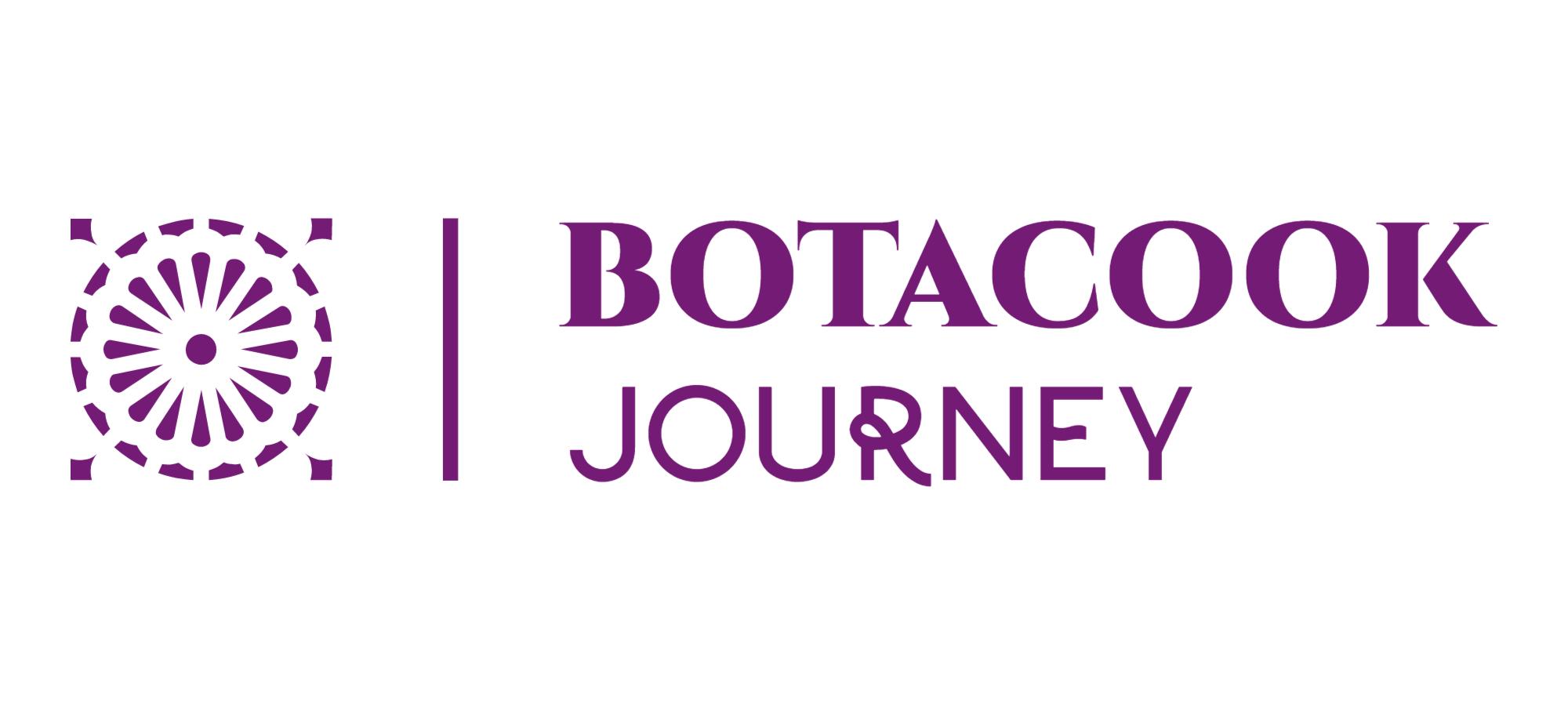日本らしい果物といわれたときに、おそらく必ず思い浮かべるのもののひとつは柿でしょう。普通は「カキ」と呼びますが、植物としての名称は「カキノキ」。日本語の分類ではカキノキ科カキノキ属になります。主に東北地方の南部から九州にかけて幅広く食用のために栽培されていますし、同時に古くから住宅の庭の植栽にも利用されている身近な果樹です。カキノキは日本、中国や朝鮮半島など東アジアの固有種であるものの、いまではニュージーランド、ブラジル、イタリアといった国々をはじめ世界中で栽培がおこなわれていて、逆に海外から輸入された種も出回っています。もともとヨーロッパやアメリカには18世紀から19世紀にかけて日本から渡ったため、学名はカキの名がそのままついたDiospyros kakiです。Diospyrosとはギリシャ語で神の果物を意味し、これはアジアから地中海地域にまで分布していた実の小さいマメガキを指してつけられた名でしょう。英語、フランス語ではkaki、イタリア語はcachi、スペイン語とポルトガル語はcaquiでいずれもほぼカキという発音です。英語ではpersimmonパーシモンとも言います。ゴルフのクラブにはウッドとアイアンという分け方があるのはご存じの通りです。ウッドと呼ぶのはもともと木製のヘッドが付いていたから。でも、現在は名前だけウッドでステンレスやチタンなど金属製がほとんどになりました。かつて木製ウッドの材料として珍重されていたのがパーシモン。今も愛用しているというゴルファーは少ないかもしれませんが、見た目も美しいのでコレクションとして大事に保管しているという人はいるでしょう。

実の生るカキの品種は非常に多く、果実によって渋柿と甘柿に分けられます。しかし食用に適した甘柿は20種ほどしかありません。その代表格が受粉に関係なく渋が抜ける完全甘柿の富有と次郎です。これとは別に受粉し種ができると渋が抜けていくのが不完全甘柿。西村早生(にしむらわせ)、禅寺丸(ぜんじまる)や筆の穂先の形をした筆柿などがあります。甘柿は渋柿の突然変異といわれており、実ができた時点ではまだ渋く、熟していくとともにだんだんと渋が抜けて甘くなります。この渋味のもとはタンニンです。お茶やワインの成分として名前を聞くことがあるかと思います。甘柿ではタンニンが水に溶けない状態になっているため、渋さを感じません。また、渋柿でも品種によってアルコールやお湯、米ぬかなどを使ったり、乾燥させたりして渋抜きをする方法が知られています。それでも渋抜きはタンニンを変化させて渋をあまり感じなくさせるだけです。加熱によって渋が戻ってしまうので、生で食べる以外の調理には向きません。柿ジャムや柿羊羹をつくるなら完全甘柿を使いましょう。

渋柿の実を圧搾した果汁を発酵させてつくる柿渋は、平安時代から染料として使われていました。防腐、防水効果があることがわかり、現在では木工品や木工建築物の下塗りや紙工芸の素材としても利用されます。カキノキ属には750以上の種があるそうです。その中でも木材として心材が黒いものを黒檀(コクタン)と呼び、建材や家具、仏壇、楽器あるいは美術工芸品の材料として珍重されます。ピアノの黒鍵などでお馴染みですね。しかし、残念ながら日本の自生種にはこの仲間はいません。コクタンはインドやスリランカそれにアフリカなどの亜熱帯から熱帯にかけて分布する常緑高木です。生長が非常に遅く、そのため材が細かく密になり、磨くと美しい漆黒の輝きがでます。ヨーロッパでは、シルクロードを通じて伝わり、高価な交易品として取引されていました。
カキはヘタで呼吸をしているので、そのためそのまま置いておくと数日で柔らかくなってしまいます。冷蔵庫の野菜室で保存する場合は、水を含ませたティッシュなどをヘタに載せて保存袋に入れるようにするといいです。