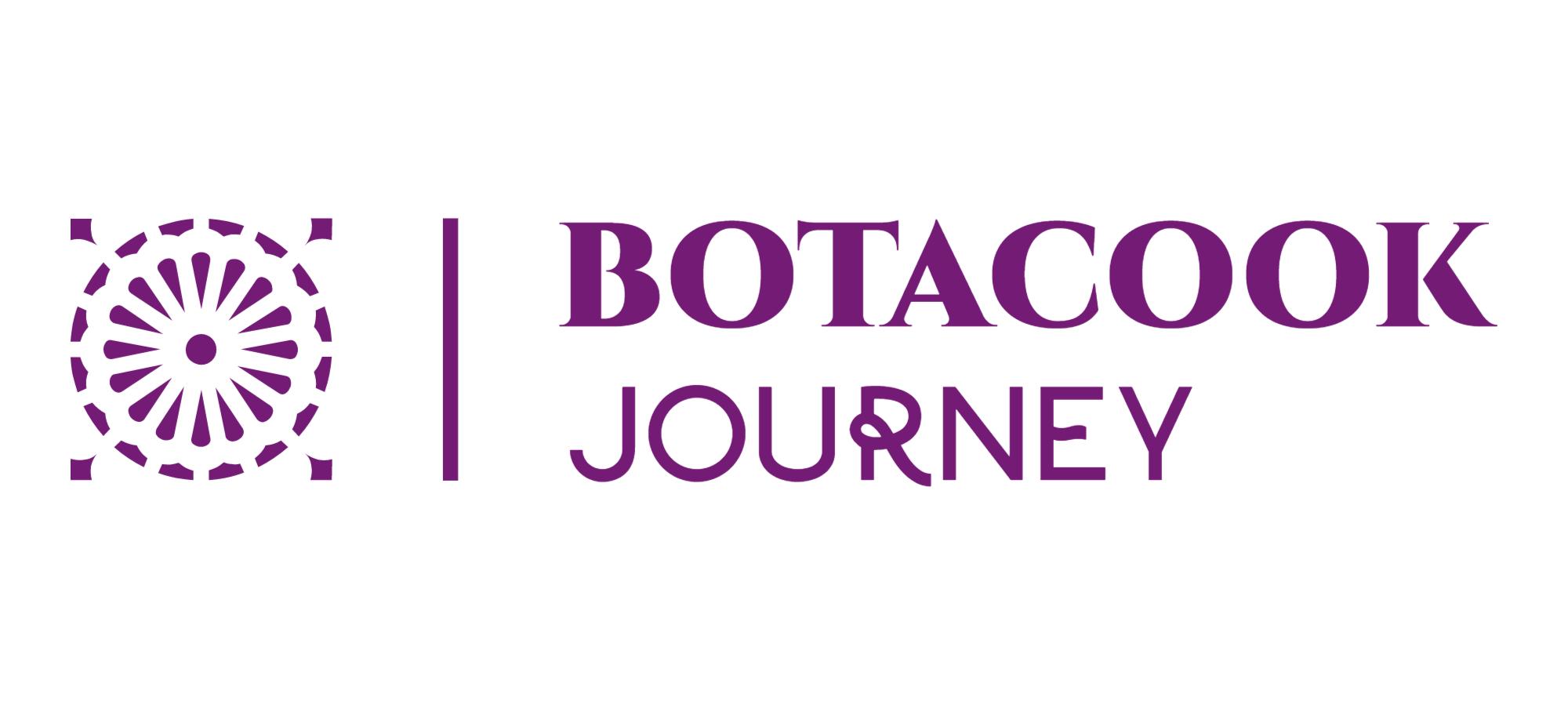スペインの南部、地中海と大西洋を臨む位置にアンダルシア州Andaluciaがあります。スペインの17ある州の中では、面積はカスティージャ・イ・レオン州Castilla y Leónに次いで2番目ですが、人口は最多です。フラメンコや闘牛、シェリー酒といったスペイン名物が多く、白い家並み、ひまわり畑といった風景でも知られています。現在のイベリア半島の大部分は、ローマ帝国崩壊後には西ゴート王国の一部でした。しかし、西ゴートが711年に北アフリカからやってきたウマイヤ朝に征服されると、イスラム教の支配下に入ります。そしてイベリア半島を指す言葉としてアラビア語でアル・アンダルスالأَنْدَلُس/Al-Andalusと呼ばれるようになったのです。その後キリスト教諸国は、イスラム教徒から占領された土地を取り戻すレコンキスタ[1]Reconquistaとは「再征服」の意味。日本の歴史の教科書では「国土回復運動」と訳されている。をはじめ、長い期間をかけて北部から徐々に領土を奪還していきます。13世紀には、イスラム勢力はいまのアンダルシアあたりまで縮小し、ついには1492年1月にナスル朝グラナダ首長国を滅ぼし、レコンキスタが完成されました。この同じ年、カトリック両王[2]カスティージャ女王イザベル1世とアラゴン王フェルナンド2世の支援を取り付けたコロンブスが、インディアスへ向けた最初の航海に出発することになりますが、それがかなえられたのもスペインに財政面での余裕がうまれたからです。

さて、ヨーロッパ大陸でのイスラム最後の拠点となったグラナダGranadaは、スペイン国内でも有数の観光地となりました。グラナダの見どころで外すことができないのは、もちろんユネスコの世界遺産にも登録されているアルハンブラ宮殿でしょう。丘の上にそびえる宮殿と庭はほとんどがイスラム時代に造られたもので、かつての輝かしい栄光を伝える美しい装飾が訪れる人々を惹きつけます。アルハンブラの名はアラビア語で「赤い」を意味するハムラلْحَمْرَاءが語源です。赤みがかった粘土でつくられた外壁の色に由来します。鍾乳石のような形状の天井や、微細な彫刻が施された壁と柱、効果的に配置された池と噴水。宮殿に隣接するヘネラリフェ庭園とともに一見の価値ありです。

グラナダの町を歩いていると、あちらこちらでザクロのマークを見かけます。実はGranadaはスペイン語でザクロという意味なのです。よく見ると市の紋章にも描かれています。町の名はザクロの実を豊富に産出するところから付けられたそうです。もともとザクロはイランからインドにかけての地域が原産とされていて、古代ギリシャの頃には広く地中海世界に伝播していました。ザクロの学名はPunica granatumです。punicaとはフェニキアのこと。古代にフェニキアと呼ばれた地中海東岸辺りからもたらされたことに由来するのでしょう。そして、Granateには種子が多いという意味があります。英語名はpomegranate。pomeとはナシ状果、つまりナシやリンゴのように、花弁や雄しべ、雌しべを支える花托の部分などが多肉となり、芯が果実になるものの総称です。ちなみにフランス語ではジャガイモをpomme de terre(terreは大地)ポム・ドゥ・テール、イタリア語ではトマトをpomodoro(oroは黄金)ポモドーロと呼びます。

ちなみに、ベネズエラ沖のカリブ海に浮かぶ島国グレナダGrenada[3]面積344㎢は、16世紀にスペインの探検家がこの島の山々がグラナダから見るシエラネヴァダ山脈に似ているとして、この地にグラナダの名を付けました。しかし、その後イギリスの植民地になった際にグレナダに変更されたそうです。この国の国旗の左側に描かれているのは、特産のナツメグNutmegの実。ナツメグは学名Myristica fragrans、ニクズク科ニクズク属の植物です。果実は硬い殻に覆われていて、熟すと半分に割れます。中の果肉の赤い表皮の部分は乾燥させてメースMaceに、内側の種子の部分をナツメグとして別々のスパイスにするのです。ナツメグはハンバーグをはじめとしたひき肉料理に欠かせませんが、メースの方はまろやかなので、お菓子やジャムに適しています。