伊丹十三が監督した「タンポポ」[1]1985年公開という映画があります。出演は山崎努、宮本信子、渡辺謙、役所広司といった錚々たる顔ぶれ。おまけに加藤嘉に大滝秀治まで出ています。流行らないラーメン屋をあの手この手で立て直すお話です。本編ももちろん面白いですが、それとは直接関係のない、食にまつわる挿話がいくつも挟み込まれています。
高級そうなホテル[2]外観はニューオータニのダイニングの一角で、岡田茉莉子演じるマナー教室の先生が生徒さんたちに向かってスパゲッティの食べ方を教授するシーンもそのひとつ。「音を立てないで召し上がっていただくわけですが…」と言ったところで、少し離れた席の外国人男性[3]演じたのはフランス人のパティシエ、アンドレ・ルコントが派手な音でスパゲッティをすすり始めました。彼女は何度も「音を立てるな」と繰り返すものの、生徒たちはかの紳士の凄まじい食べっぷりに引きずられるようにして一斉に麺をズルズルとすすり出します。挙句には先生も豪快な音を立てながら競うように口へ運ぶことに。これは表面的には、堅苦しいマナーなど関係なく好きなように食べればいいというような意味でもありますが、実はそれだけではありません。もうひとつ伊丹ならではの含意があるのです。
伊丹十三が初めて出版したエッセイ集「ヨーロッパ退屈日記」[4]1965年刊行の中に、「スパゲッティの正しい食べ方」なる節があり、そこにはスパゲッティを音もなく食べるテクニックが書かれています。子供の頃から、母にスパゲッティはすすらずフォークに巻き取るとは教わっていたものの、なかなかうまくできず適当に食べていました。ところが高校時代にこの本を読んで、目から鱗が落ちるとはこのことだと思ったのです。要はお皿の一部に小さなスペースをつくり、そこに数本のスパゲッティを引っ張ってきて巻き取るという方法。正にこれはイタリアでは普通のことで、お皿の上にフォークを立てるようにすれば必要な分だけきれいに巻けます。スパゲッティの塊の中にフォークを突っ込んだり、一度にたくさんフォークに絡めたりすると上手にできません。巻き取れたつもりでも、フォークからスパゲッティが垂れ下がっていては失敗です。フォーク一本で巧みに食べるためには、①スパゲッティ全体を少し押しやって手前に巻く場所を用意すること、②5~6本ぐらいずつ取ってくること、③きれいに巻けなければやり直すこと、がポイント。フェデリーニfedeliniやリングィーネlinguine、ヴェルミチェッリvermicelliなどのロングパスタpasta lungaはみんな同様です。イタリアのお店ではこれをやり易いように、スパゲッティなどは平らな皿で提供するのが当たり前となっていて、スープボウルのような深い皿で出されることはまずないでしょう。

映画では先生がフォークとスプーンを使って巻き取る方法をお手本として伝授するのですが、伊丹はそれをエッセイの中で「違反ではない」とは述べているものの、美しくない、粋でない、イタリア的でないと考えていたに違いありません。なぜなら、イタリア人は絶対にやらないから。「気取ったところで何もわかってないじゃない」と言いたいわけです。実際に、イタリアのレストランでスパゲッティを注文した場合にスプーンを用意されることはあり得ないでしょう。頼めば出してくれるとは思います。でも、スプーンの上でクルクルしているのを周りのテーブルのイタリア人は奇異の目で見るかもしれませんし、従業員たちは店の奥で笑っているかもしれません。その土地の正しい、あるいは実用的なお作法を心得るべしということです。郷に入っては郷に従え。たとえイタリア人でも日本に来たらそばやうどんやラーメンをすすってみろ、日本人もイタリアに行ったらスパゲッティを上手に巻いて食べろという意味でもあります。
そもそも欧米の食事作法では、フィッシュスプーンはともかく、スープとデザート以外の料理にスプーンを使うのはフォークがまだ上手に使えない小さい子供だけと考えます。なのでスパゲッティを巻くためであってもスプーンの助けを借りずにフォークのみで食べるべきですね。ちなみに拙宅ではカレーライスもフォークで食べます。
本当のところ、イタリアでもスパゲッティをフォークにきれいに巻き取って食べるようになったのはそれほど昔のことではありません。フォークが食事で使われるようになったのは、17世紀フランスのルイ14世の影響によると言われます。そして18世紀末に、シチリア王フェルディナンド3世[5]在位1759年-1819年・ナポリ王フェルディナンド4世の側近が、ナポリでよく食べられていたスパゲッティを食べやすくするため、それまで3本が主流だったフォークのプロング(爪)を4本に増やしたのだそうです。それでもフォークを使って食事していたのはごく少数で、庶民は手づかみで食べていました。誰もがフォークで食べるようになるのは、フォークが大量生産され廉価で入手が可能になった20世紀に入ってからです。

1954年のイタリアのコメディ映画”Miseria e nobiltà”(貧困と高潔)[6]日本未公開・主演トト、ソフィア・ローレンでは、19世紀後半のナポリが舞台。伯爵に頼まれて彼の家族に成りすました貧しい人たちが、豪華な食事を出されてスパゲッティを手づかみで貪り食うという場面が良く知られています。
もうひとつ同じ1954年の”Un Americano a Roma”(ローマのアメリカ人)というイタリアのコメディ映画[7]日本未公開。その中の最も有名なシーンが、主役のナンドがパスタを食べるシーンです。イタリアへ旅行した方は右下の写真を目にしたことがあるかも。アルベルト・ソルディAlberto Sordi演じるナンドは、アメリカかぶれの青年。いずれアメリカへ行くことを夢見て、本人はアメリカ人になりきっているつもりです。母親が彼のために用意しておいた夕食の「マカロニ」に悪態をつき、彼がイメージするアメリカ人の食べ物としてパンにマーマレードとヨーグルトとマスタードと牛乳をかけて食べます。不味くて食べられず、マカロニに「お前をやっつけてやる」と言いながらかきこむシーンがこれ。実際にはロングパスタ[8]調べたところブカティーニらしいですが、アメリカ人はパスタをなんでもマカロニと呼ぶ[9]イタリアでもかつてはマカロニとパスタは同義語でしたとか、アメリカ人は力強く豪快に食べるとかという思い込みの表現です。第二次世界大戦で敗れたイタリアには、戦後、アメリカ人とアメリカ文化が怒涛の如く押し寄せます。この映画はそんなアメリカに憧れる人々への皮肉であり、アメリカ文化に対しての風刺でもあるのでしょう。

伊丹はスパゲッティに関して、「ヨーロッパ退屈日記」の「スパゲッティの正しい調理法」「息詰まる十分間」や「女たちよ!」[10]1968年刊行の「スパゲッティのおいしい召し上がり方」にも持論を述べていますし、「みんなでカンツォーネを聴きながらスパゲッティを食べよう」なるサウンド・エッセイ集も出しています。

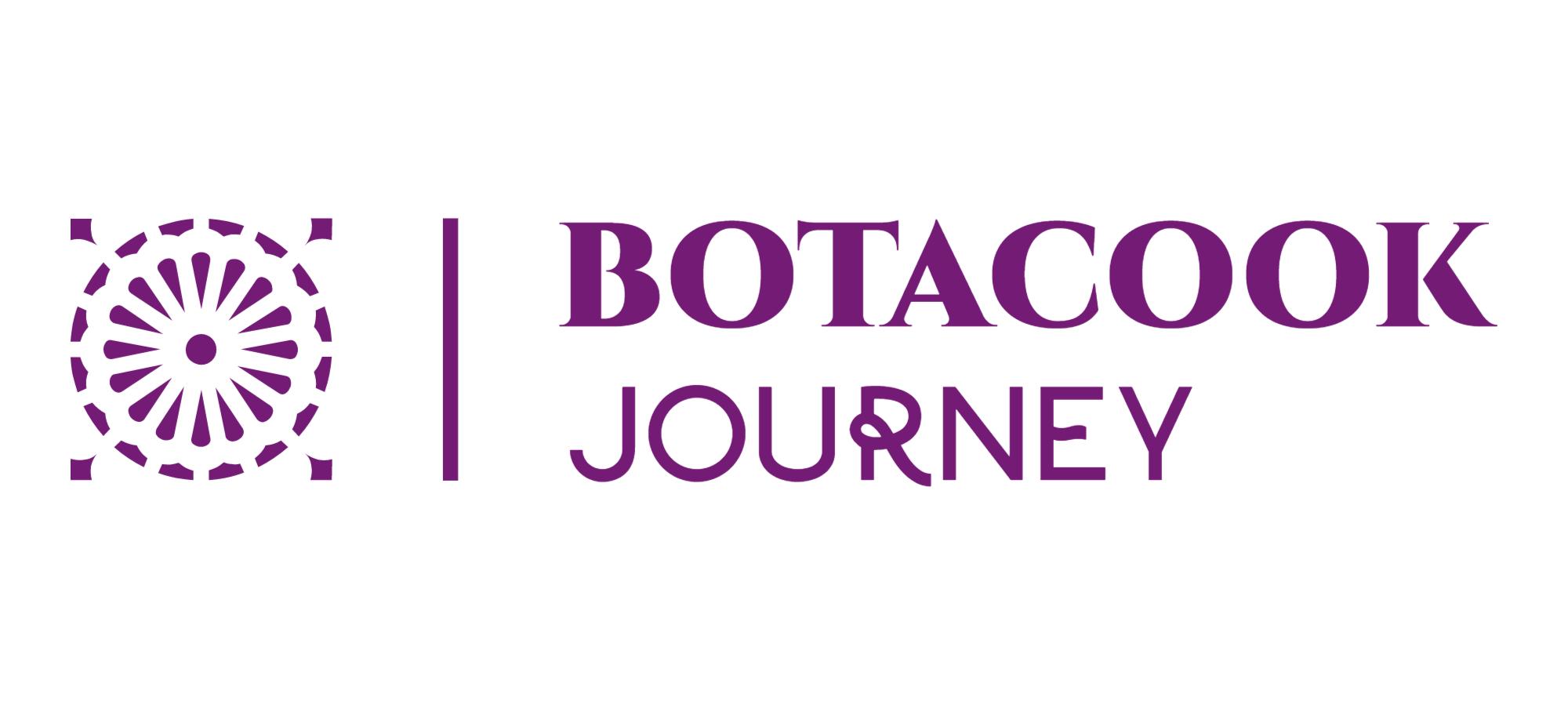
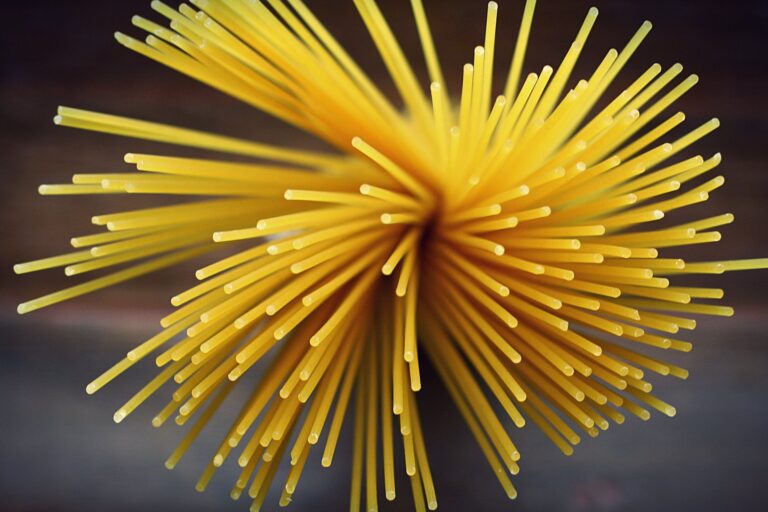
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3bae.83238834.217b3baf.07b3dcac/?me_id=1213310&item_id=11347502&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1011%2F10116731.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3bae.83238834.217b3baf.07b3dcac/?me_id=1213310&item_id=11347503&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1011%2F10116732.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/39cfad0a.ed48a400.39cfad0b.f5cbc15d/?me_id=1352607&item_id=10427640&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcometostore%2Fcabinet%2F20201107-2%2Fb0002883po.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)