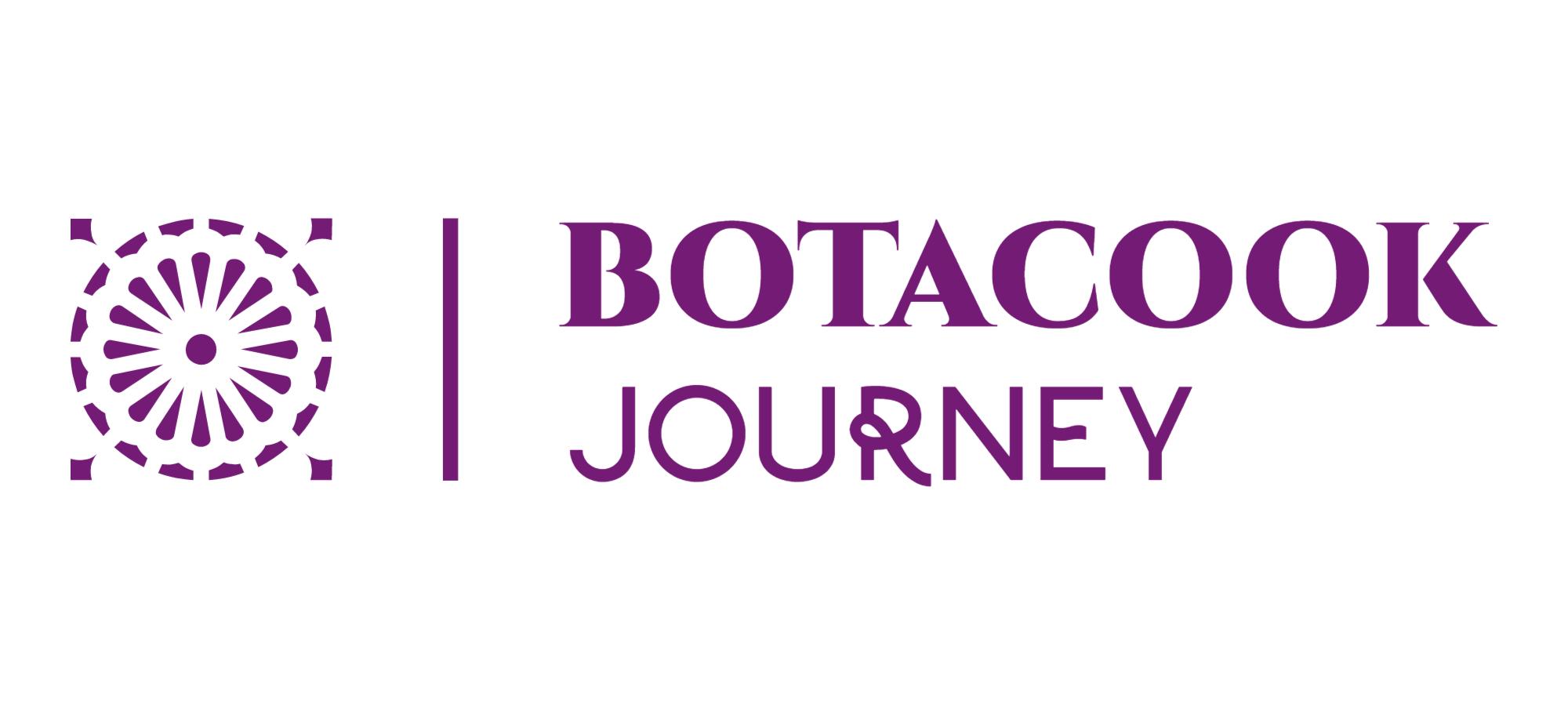日常の食卓に欠かせない野菜のひとつです。鮮やかなオレンジ色が他の食材と合わせたときにより引き立ちます。和食にも洋食にもその他の料理にもニンジンを使ったものは豊富にありますし、ジュースやスイーツもいいですね。ニンジンは東洋種と西洋種に大別されます。東洋種はいまのイランやアフガニスタンの辺りが原産地とされ、もとは紫や黒に近い色で、その後に黄色が出現したとのこと。細長いのが特徴です。日本には中国経由で江戸時代に伝わり、栽培がおこなわれてきました。おせち料理によく使われる紅色の金時ニンジンがよく知られています。西洋種のほうは、黄色の東洋種をもとに作られた品種で、現在一般的に売られているオレンジ色のニンジンです。16世紀にオランダで生まれたとされます。オランダ語でニンジンはwortelヴォルテル。実は、オランダ語ではこの単語は植物の根のことも意味します。ニンジンは根菜の代表ということでしょう。ちなみにオレンジ色が大好きなオランダ人ですが、ニンジンの色との関わりはないみたいです。

日本でも普通に流通しているニンジンと言えば明治以降に入ってきた西洋種。主流になっているのは五寸ニンジンです。食用部分の根の長さが五寸(約15㎝)前後だからその名があります。以前住んでいた家の近くの畑では、短い三寸ニンジン[1]江戸東京野菜の馬込三寸ニンジンを栽培していました。ニンジンは農林水産省が定める14品目の指定野菜のうちのひとつなので一年中入手可能です。東京だと夏場は北海道産、冬場は千葉県産が多いと思います。

ニンジンと言えば緑黄色野菜の代表格で、βカロテンβ-caroteneがたっぷり含まれていることで有名。カロテンは体内に吸収されると一旦蓄えられ、必要に応じてビタミンAに変化します。抗酸化作用とともに、皮膚や粘膜を強くしたりする効果も。カロテンは1831年にドイツのヴァッケンローダーWackenroderという化学者によって、ニンジンのラテン語名carotaカロタから名付けられました。このカロテンから、黄色、オレンジ、赤の天然色素であるカロテノイドcarotenoidという言葉も生まれたのです。ニンジンのカロテンの成分は皮の近くにより多いので、皮は剝かずに食べたほうがたくさん摂取できます。また、カロテンは脂溶性です。油とともに調理すると吸収されやすくなります。
ニンジンはセリ科の植物です。セリ科には、野菜として扱うセロリやミツバ、パセリ、アシタバなどのほかに、クミン、フェンネル、ディル、コリアンダー、キャラウェイ、チャービルといった多くのお馴染みのハーブ類が含まれます。いずれも独特の芳香があって、上手に使うと料理を一段と味わい深いものにしてくれますね。中でもパクチーや香菜とも呼ばれるコリアンダーは好き嫌いが分かれるものの、東南アジア系のエスニックをはじめとして、中国料理、それに中東、南欧、中南米など世界各地の料理に使われています。料理に利用する切れ込みのある葉は、根元に生える若葉です。茎から出る葉は糸状になります。

References
| ↑1 | 江戸東京野菜の馬込三寸ニンジン |
|---|