イングランド南部の小村セント・メアリー・ミードで人生の大半を過ごしてきたジェーン・マープルは、落ち着いてひとの話に耳を傾け、じっくりと観察します。そして、気に掛った些細な事象に着目しては快刀乱麻を断つが如くに謎を解いていくのです。そんな、老いてなお矍鑠(かくしゃく)としたミス・マープルが才気を発揮するお話を個人的視点でご紹介します。(内容は早川書房版をベースにしています)
◆牧師館の殺人The Murder at the Vicarage(1930年)
ミス・マープルがはじめて登場する長編小説。セント・メアリー・ミード村の牧師レナード・クレメントがストーリーテラーになります。セント・メアリー・ミードSt.Mary Meadは架空の村です。ロンドンから25マイルほどの距離にあるとされています。ミードmeadとは蜂蜜酒のこと。蜂蜜色の石積みの家並みが目に浮かびます。
このお話のストーリーテラーとなるのは教区牧師vicar(ヴィカ)のレオナルド・クレメントです。牧師館vicarage(ヴィカリジ)にはレオナルド牧師一家が住み、すぐ裏手にはミス・マープル宅があります。レオナルドよりも20歳以上年下の妻の名はGriseldaグリゼルダ。レオナルドは牧師の妻にふさわしい名前だと思いながらも、”She is not in the least meek.”「彼女はちっとも従順ではない」と言っています。グリゼルダというのは、ボッカッチョの「デカメロン」10日目の10番目、つまり物語の最終話に登場する貞淑な妻です。もともとは忍耐と従順を説く民間伝承のかたちで存在していたものを取り入れたとされ、グリゼルダの話はペトラルカやチョーサーの作品にも見られます。牧師夫妻は息子とともに「書斎の死体」“The Body in the Library”(1942年)で再登場。グリゼルダは「パディントン発4時50分」”4.50 from Paddington”(1957年)にも未亡人として出てきます。
ある日の夕刻、偽の電話で呼び出された牧師が留守の間に、牧師館の書斎でプロザロー大佐が頭を拳銃で撃たれて亡くなりました。プロザローは教区委員でありセント・メアリー・ミードの治安判事でもあるお金持ちです。そして牧師館の敷地内にアトリエを持つローレンス・レディングが警察に自首します。しかし、ローレンスは殺害時刻には現場にいなかったことが分かっているので、誰かをかばっているのかもしれません。プロザローの若い後妻アンはローレンスと浮気をしているという噂もあるようです。一方、村の女性たちは、集まってはお茶を飲みながら世間話に花を咲かせます。そのうちのひとりがミス・マープル。彼女は、犯人として疑わしい容疑者は7人いると言います。プロザローはそれほど殺されうる理由を持っていた人物だったということでしょう。
ローレンスが釈放された後のある日、牧師が茂みの中を歩いていると大きな石を抱えているローレンスに出会います。彼が言うには、その石は日本庭園を造っているミス・マープルへの”peace offering”だそうです。この言葉は「貢ぎ物」(2022年初版東京創元社版では「社交上の貢ぎ物」)と訳されていますが、少し説明が必要だと思います。英語の意味は「仲直りの印」とか「和解の品」としてのプレゼントのこと。ただし、これはもともと旧約聖書にも出てくるユダヤ教では重要な言葉です。ヘブライ語でZevaḥ shelamim(ゼヴァ・シェラミム)と言います。神への犠牲や供物の捧げ方には細かい決まりがあり、モーセ五書のひとつレビ記の第1章から第9章にかけてその詳細が記されているのです。モーセたちは神に近づくために、命じられたとおり、燔祭(はんさい[1]捧げものを全て焼き尽くす)、素祭(そさい[2]動物などと合わせて捧げる穀物)、罪祭(ざいさい[3]贖罪のための捧げもの)、愆祭(けんさい[4]賠償のためもの捧げもの)、酬恩祭(しゅうおんさい[5]神のみ恵に感謝するための捧げもの)の5種の祭祀を執り行いました。このうちの酬恩祭がpeace offeringです。酬恩祭で捧げられるのは家畜の牛や羊や山羊。人々は酬恩祭で神に感謝し、正しい手順で捧げた肉しか食べることができませんでした。つまり単なる「貢ぎ物」ではなく、「神と民とが分け合うもの」だというところが大事。それが仲直りであり和解であるとなったのです。果たしてローレンスはミス・マープルへのどんな思いを表現したのでしょうか。でも、ミス・マープルが日本庭園とは些か信じ難い部分もあります。実際に彼女は後に、ロック・ガーデンだと述べているのでローレンスの勘違いかも。
ちなみに燔祭の英語はholocaustホロコースト。「すべて燃やす」という意味のギリシャ語からきています。そこから転じてナチス・ドイツに代表される大虐殺を表すようになりました。
さて、7人の容疑者の中に真犯人はいるのか。ミス・マープルは、プレザローの書きかけの手紙、壊れた時計、聞こえなかった銃声などの謎を解き明かし真相に近づくのです。

いよいよ謎解きの段になり、ミス・マープルが趣味について語ります。
“There is, of course, woolwork, and Guides, and Welfare, and sketching, but my hobby is ― and always has been―Human Nature. So varied―and so very fascinating. And, of course, in a small village, with nothing to distract one, one has such ample opportunity for becoming what I might call proficient in one’s study.”「まあ、当たり前には、刺繍やガイド(ガールガイド[6]日本やアメリカのガールスカウト)、福祉活動、それに写生なんかがありますねぇ、でも私の趣味は、ずっとそうなんですけど、人間性なのよ。すごく多様でとっても魅力的です。それに、もちろん、小さな村では気を散らすことがないですから、いわゆるその道の達人になるための十二分な機会があるんですよ」この人間観察を趣味とするお婆さんだからこそ卓越した推理を構築していくことができるのでしょう。
◆予告殺人A Murder is Announced(1950年)
10月29日金曜日の朝、絵のように美しいと形容されるチッピング・クレグホーン村の地方紙、チッピング・クレグホーン・ギャゼットの個人広告欄にこんな記事が。
“A murder is announced and will take place on Friday, October 29th, at Little Paddocks at 6.30 p.m. Friends please accept this, the only intimation.”「殺人のご案内です。10月29日金曜日にリトル・パドックスで午後6時30分に挙行されます。身内の方はどうぞ応じてください。お知らせまで」当日の殺人の予告と招待という内容です。これを読んだ村の人々は「殺人ゲーム」が行われるのだと思います。
リトル・パドックスに住むのは、女主人のレティシア(通称レティー)・ブラックロック、その旧友ドラ・バンナー、レティシアのいとこのパトリックとジュリア、下宿人のフィリッパ、それに家政婦のミッチー。誰も広告を出した覚えはありません。でも大勢の人がやって来ると予期して受け入れの準備をします。ミッチーは若い避難民です。Mitziという綴りでグヤーシュをつくると言っているので恐らくハンガリー人でしょう。
リトル・パドックスを訪ねてきたのは、イースターブルック大佐夫妻、農場を経営するミス・ヒンチクリフとミス・マーガトロイド、若い作家エドマンドとその母スウェッテナム夫人、牧師の妻ダイアナ・ハーモンという面々。集まった人たちが一体何が起きるのかと待っていると、6時30分になって置き時計が鳴ります。その瞬間、部屋の明かりが消えて、暗闇の中で事件が起きるのです。怒号と銃声。弾丸がかすめたのかレティシアの耳からは血がしたたり落ち、賊と思しき男が倒れています。自殺のようです。警察の調べで、死んだ男はロイヤル・スパ・ホテルに勤めるスイス人のルディー・シャーツだとわかります。事件を担当するクラドック警部は現場にいた者たちに対して、順番に事情聴取を開始。するとレティシアがロイヤル・スパ・ホテルでシャーツから声をかけられ、面識があると言われたことも判明します。彼女は病気の妹シャーロット(通称ロティー)とともにモントルーのホテルにいたことがあり、シャーツはそこのオーナーの息子だと称したとか。しかし、最近シャーツがお金の無心にやって来て迷惑したとも。
やがて警察署長のところへミス・マープルからお手伝いをしたい旨の手紙が届き、クラドックが元警視総監ヘンリー卿と一緒に面会しました。ヘンリー・クリザリング卿は「火曜クラブ」The Thirteen Problems(1932年)からのお馴染みで、ミス・マープルに絶大なる信頼をよせています。クラドックも「鏡は横にひび割れて」The Mirror Crack’d from Side to Side(1962年)では再登場です。クラドックの丹念な捜査と、彼に疎まれながらもミス・マープルが与える的確な助言で徐々に明るみに出てくる事実。シャーツの本当の素性や、誰かに利用されてその人物によって殺されたのであろうことがわかってきます。

レティシアはかつて資産家ランダル・ゲドラーの秘書でした。彼の莫大な遺産は妻のベルが相続しましたが、彼女が亡くなったらすべてはレティシアに引き継がれることになっています。けれども、ベルより先にレティシアが死んでしまった場合には、その遺産はランダルの妹ソニアの双子の子供ピップとエンマのものとなるそうです。これが動機に繋がるのでしょうか?
そして発生する第二、第三の殺人。被害者たちは何かを見たため、あるいは何かを知ったために殺されてしまったのでしょうか?大勢の人が入り乱れるストーリーではあるものの、きちんと読んでいけば何かしら真相へのヒントが見えてくるかもしれません。
さて、事件もすっかり解決した23章の終わりに、ハーモン牧師が誤訳だと語る”Voice of the turtle”「亀の声」のくだりが気になりました。これは旧約聖書の雅歌[7]英語ではSong of Songs(第2章12節)にある、春になって花が咲き、鳥が鳴くという部分です。聖書の日本語版では山鳩(やまばと)になっているので、英語版をいくつか見てみると、turtledoveあるいはdoveなのですが、ジェームズ王訳(欽定訳聖書・1611年初版)では確かにturtleでした。

ついでに、フィリッパに恋するエドマンドが彼女を賛美して口ずさむ、アルフレッド・テニソン男爵の”Maud”「モード」の一節を。
“Faultily faultless, icily regular, splendidly null,
Dead perfection, no more.”
「欠点のないところが欠点、氷のように整い、見事なほど空虚、それ以上なく極めて完璧」(拙訳)
◆魔術の殺人They Do It with Mirrors(1952年)
ミス・マープルはロンドンの高級ホテルへ、アメリカ社交界のルース・ヴァン・ライドックを訪ねます。ルースと妹のキャリイ・ルイーズはミス・マープルのフィレンツェでの寄宿学校時代からの友人です。彼女は妹のことを気に掛けるルースからの頼みで、キャリイ・ルイーズの住むStonygatesストニイゲイツに滞在することになりました。ストニイゲイツは、キャリイ・ルイーズの最初の夫グルブランドセンが遺したヴィクトリアン様式の立派な邸宅。現在は、彼女の三番目の夫ルイス・セロコールドが運営する非行少年のための更生施設を併設しています。キャリイ・ルイーズとともに暮らすのは、亡くなった養女の娘ジーナとその夫ウォルター、実の娘ミルドレッド、二番目の夫の連れ子スティーヴン、彼女の身の回りの世話をするジュリエット、精神科医のマヴェリック博士、それにひと月ほど前にやってきてルイスの手伝いをする元非行少年エドガー・ローソンなどの面々。ミス・マープルは早速その人々と関わり、絡み合う人間模様を知るのです。
ある日の午後、突然にグルブランドセンの息子クリスチャンがやって来ました。クリスチャンとルイスは施設を運営するグルブランドセン協会の理事を務めており、どうやらクリスチャンはルイスに大事な話があるようです。夕食後、クリスチャンは大切な手紙を書くからと先に部屋へ戻ります。その他の人たちは順に食堂を出てホールへ。ウォルターが読書灯のスイッチを入れたところヒューズが飛んだらしく、ホールの電灯が半分ほど消えてしまいました。すると、そこへ入ってきたエドガーがルイスに向かって罵りはじめたので、ルイスはエドガーを伴って隣の書斎へ入ります。エドガーは虚言癖があり精神を病んでいるとみられているのです。ホールにいる人たちには興奮して喚き散らすエドガーとそれをなだめるルイスの声が聞こえます。やがて中から二発の銃声が。そして射殺死体が発見されるのですが、亡くなったのはエドガーでもルイスでもなく別の部屋にいたクリスチャン。
警察がやって来て捜査が開始されるものの、誰がどのような方法で殺害したのか皆目見当が付きません。しかし彼らはミス・マープルの慧眼な能力に気付き、彼女の指摘するところに着目して推理を展開していくのです。
スティーヴンにも犯人の疑いがあることに対してキャリイ・ルイーズがそんなことはないと繰り返す場面で、カリイ捜査官が思うのは祖母のよく言っていたことわざ。
“Pigs may fly, but they’re very unlikely birds.”
「豚が空を飛ぶかもしれない、鳥みたいになれることはないにしても」
つまり絶対ないとは言い切れないということです。スコットランドのことわざだとか。
“Pigs may fly”や”When pigs fly”というのは不可能や無理を意味する言い回しとしてよく使われます。
“Through the Looking Glass : and what Alice found there”「鏡の国のアリス」[8]ルイス・キャロル著・1871年初版の中の”The Walrus and the Carpenter”「セイウチと大工」で、セイウチが小さな牡蠣たちに向かっていろいろな話をしようとする場面で言うのは、”…and whether pigs have wings”「それに豚に翼があるかどうかとか」。ありもしない与太話もあるよという感じでしょうか。

アガサのこの著作は、アメリカで出版された際には”Murder with Mirrors”「鏡を使った殺人」というタイトルでした。原題”They Do It with Mirrors”、直訳すると「彼らは鏡を使ってそれをやる」とは違ってミステリっぽいです。ただしこのお話の内容は鏡を使う殺人事件ではなく、日本語のタイトルに近いと言っていいでしょう。殺人のトリックを魔術師が見せるイリュージョンの仕掛けに譬えているわけです。
“‘Like magicians,’ Miss Marple said. ‘They do it with mirrors is, I believe, what people say.'”
『「魔術師のように」ミス・マープルは言った。「よく言うと思うんですけれどね、あいつらは鏡を使っているんだって」』

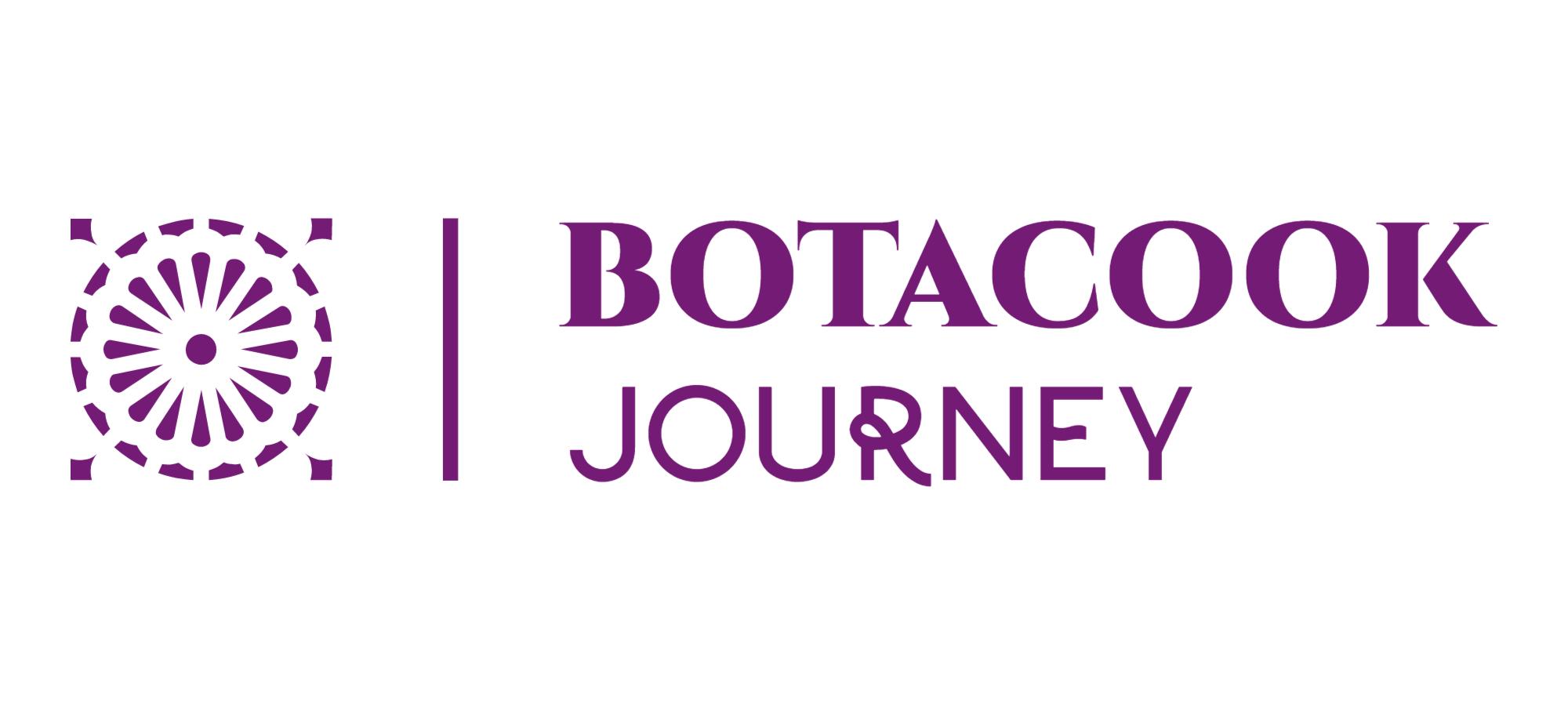
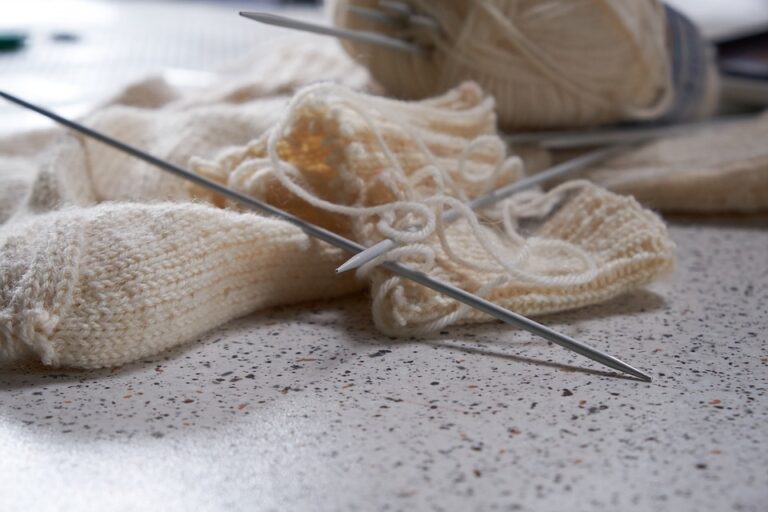
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3bae.83238834.217b3baf.07b3dcac/?me_id=1213310&item_id=14725880&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0355%2F9784151310355_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/217b3bae.83238834.217b3baf.07b3dcac/?me_id=1213310&item_id=19967422&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0386%2F9784151310386.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/36ec21c5.51fd11aa.36ec21c6.a869c5c5/?me_id=1249489&item_id=10866767&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fcomicset%2Fcabinet%2F05426072%2Fbkrjvv2xjuxil35a.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)