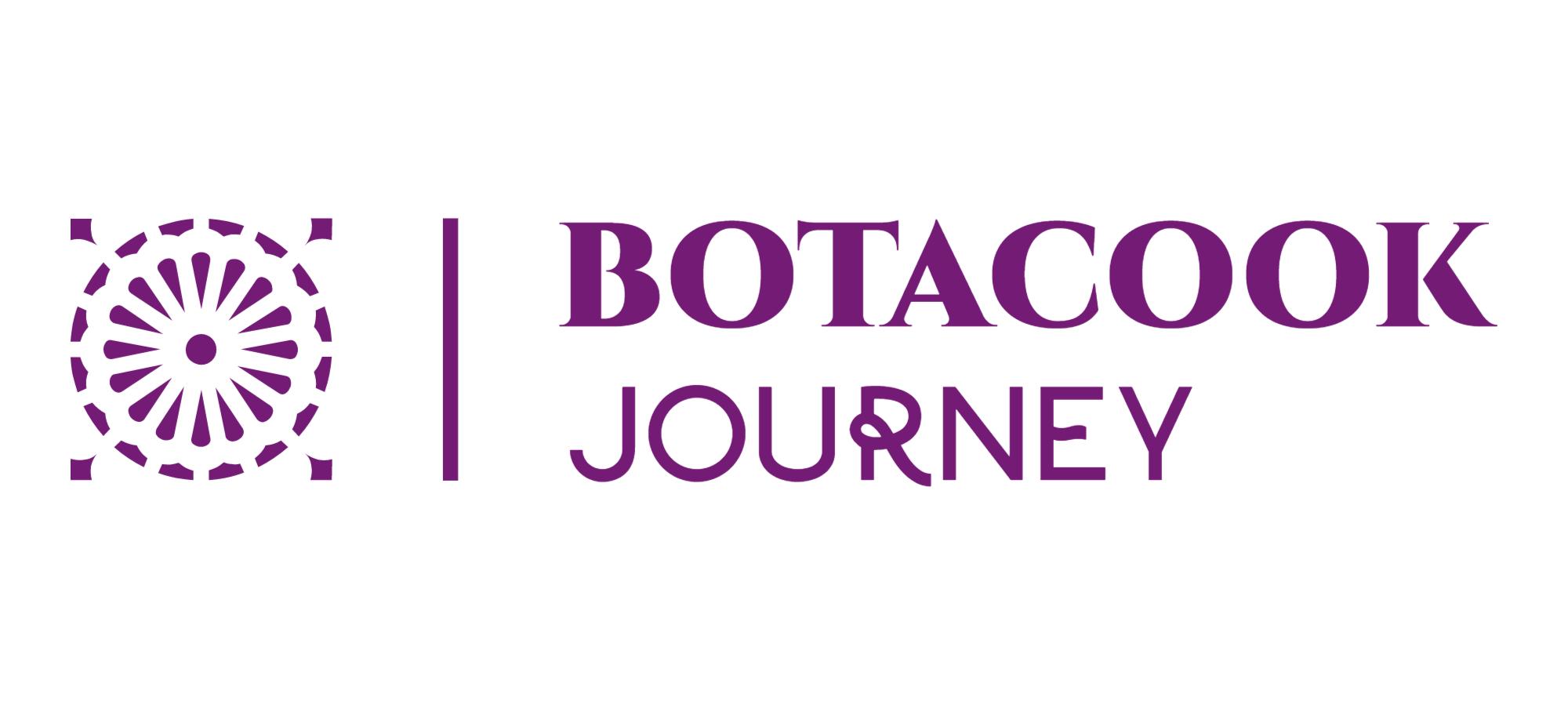12月21日または22日は、北半球で一年のうち昼がもっとも短く夜がもっとも長くなる冬至の日です。昔からゆず湯に入り、カボチャを食べるという習慣がありますね。日本だと南北での差異を考慮したとしても、日の出から日の入りまでは9時間から10時間はあるでしょう。ですから、そこまで暗さを実感することはあまりないかもしれません。一方、同じ時期のヨーロッパを訪れると、まず一際暗いことに驚きます。朝になってもなかなか明るくならず、午後はあっという間に日が傾きすぐに夜がやって来るのです。それもそのはず。日本の最北端の宗谷岬が北緯45度31分なのに対して、パリは北緯48度51分、ロンドンは北緯51度30分という高緯度に位置するからでしょう。ちなみに東京は北緯35度41分にあり、地中海地域に当て嵌めると、スペイン南端を越えたモロッコのタンジェあたりです。そのため、ヨーロッパの特に中部から北部では、短い夏が終わるとどんどんと暗く寂しくなって、人々の気持ちも沈んでいきます。なので、冬至を過ぎて徐々に明るさを取り戻していくことが、生命のはじまりや再生につながると考えられました。太陽への信仰とともに冬至を祝う習慣が根付いていったわけです。
このように、古来より取り分け北欧を中心としたゲルマン諸民族の間では、冬至がそれを境に新しい太陽が生まれる日であることから、新しい年の始まりとされていました。毎年、12月から1月にかけての期間には、それを祝うユールJul, jól(英語ではyule) と呼ばれるお祭りが開催されていたのです。これがのちにキリスト教の普及に伴い、クリスマスのお祝いと融合するように変化したのだといわれます。スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語でクリスマスを意味する単語はjulです。
そして、現在もスウェーデンやデンマークなどのスカンジナヴィア諸国で祝われる聖ルチア祭。これは伝統的に、かつての古い暦であるユリウス暦[1]ユリウス・カエサルが制定し、グレゴリウス暦に入れ替わる16世紀まで使用されたで冬至にあたる12月13日に行われます。聖ルチアとは、古代ローマのディオクレティアヌス帝[2]在位284-305時代に、シチリア島のシラクサで殉教した聖女です。彼女の死後、各地へとその信仰が広まり、ナポリでは船乗りの守護聖人とされて、有名なナポリ民謡「サンタ・ルチア」も作られました。さらにキリスト教が広まるとともに、聖ルチアの名も知られるようになり崇拝が盛んになります。もともとは遠く離れた北欧とは縁がなかったわけですが、ルチアの名がラテン語の「光」luxおよび「光の」lucisという言葉から派生していることや、その記念日が12月13日ということなどから、ユールと結びつき冬の一番大切な行事として定着していったのです。スウェーデンでは、白いドレスをまとった少女がろうそくを付けたリースの冠をかぶった姿で集まり、歌を歌ったりお菓子を配るという催しを学校や教会あるいは町内で行います。スウェーデンの聖ルシア祭で欠かせないのが、lussekatterルッセキャッタ(ルシアの猫)と呼ばれるサフラン風味のパン。丸まった猫を模したものだそうで、レーズンを目に見立てています。

古代ローマでは毎年12月17日から23日の期間に、農業や豊穣の神サトゥルヌスに捧げるサトゥルナリア祭が開催されていました。さらに、アウレリアヌス帝[3]在位270-275によって12月25日が太陽神ソル・インヴィクトゥスの祭日と定められます。またローマでは、古代インドやペルシャから伝わったミトラ教の信仰も広がっていて、太陽神ミトラがソル・インヴィクトゥスと習合したかたちで、太陽神の再生の日として冬至を祝うことも行われたのです。一方、初期のキリスト教では、イエス降誕の日付は特定されていませんでした。4世紀にはイエスの降誕の日が12月25日と定められ、ローマの神々の祭日と融合するようなかたちでこれを祝うようになったといわれます。このように、かつてキリスト教を伝道した人々は、広く世界へとその教えを伝えていこうとする中で、その土地の伝統や慣習を取り入れて結び付けていく手法を取りました。そのため、ゲルマン諸部族に対しての布教を行ううえでは、冬至とキリスト教の結びつきは必然として強くなっていったと考えられます。つまり冬至とクリスマスの関係は、キリスト教の中に特定の宗教や神の影響が顕著に現れているわけではなく、数々の伝統的信仰などが合わさることによって幅広く認められていったということでしょう。
クリスマスにはクリスマスツリーを飾ります。これもやはりユールのお祭りで生命の象徴として飾られたモミが起源とされるのです。クリスマスツリーが一般化されるのは16世紀以降のことで、ドイツからその習慣が広まったといわれます。欧米ではいまでもツリーは生の木が主流で、樹種はモミだけでなくトウヒやアカマツ、サワラなども使われ、専門の農場もあります。