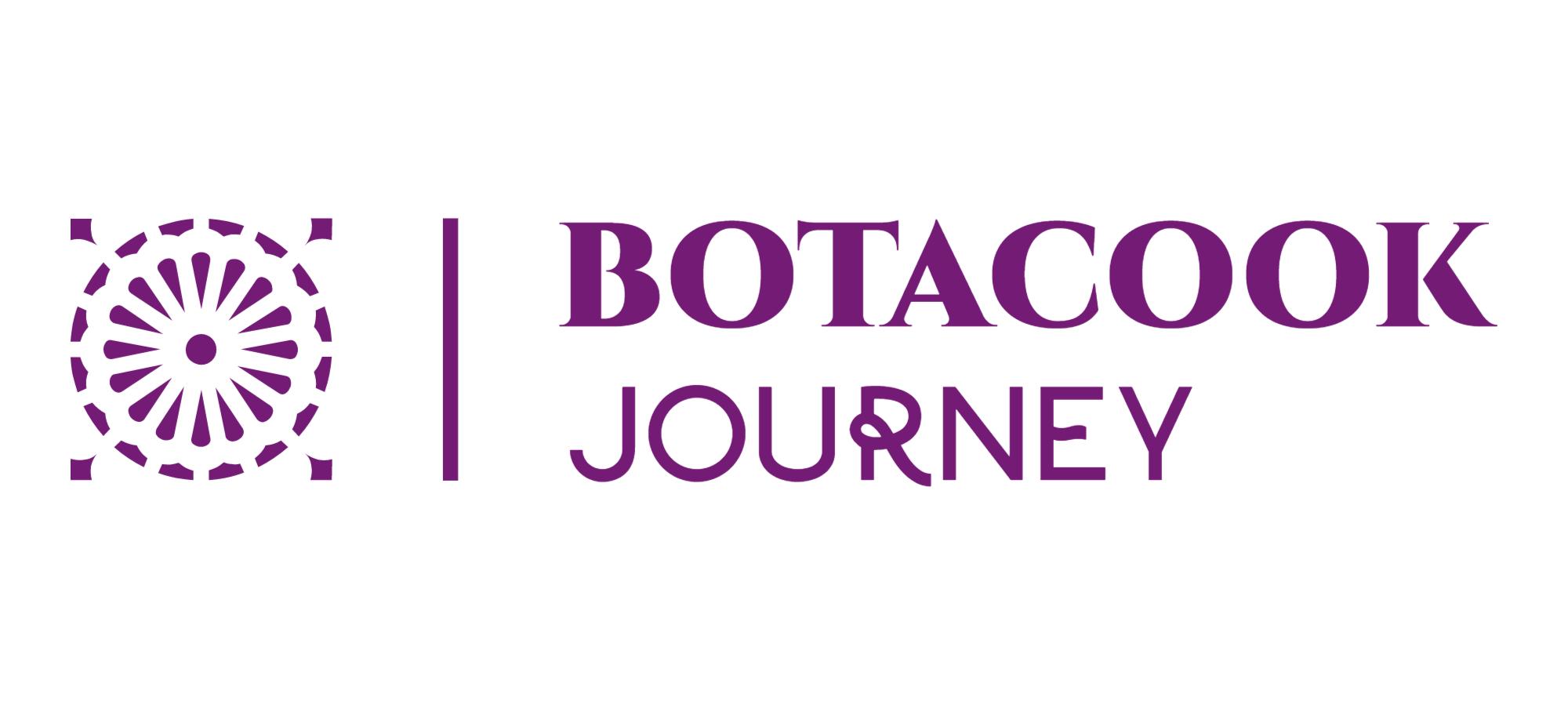植物の生育には土が必要です。空気中や水中に根をのばす一部の植物は別にすると、ほとんどは土の中に根を張り、そこから生長に有効な成分を吸い上げています。植物が健康に育ち、花や実をつけるためにはその基盤となる土が良い状態でなければなりません。
ではどんな土が良い土といえるのでしょう。とりあえず手近にある土を触って観察してみるとわかります。色はどんな感じでしょうか。少し水を含んだ状態で黒に近い濃い褐色というのがもっともよい土の色です。黄色っぽかったり白っぽかったりするのは成分のバランスがあまりよくありません。ヌルヌルしていれば粘土質ですし、ザラザラしていれば砂質ということになります。その土を手の中で握ってみましょう。団子状になってそれでも簡単に突き崩せるぐらいの粒の集まりというのが理想的です。固まらずにバラバラだったり、逆に固まったままだったりする場合にはやはりバランスが悪いと考えられます。実際に植物を育てる場所では、地表部分だけではなく、もう少し下の、植物が根をのばす深さの土の状態も調べてあげるべきです。粘土質の場合には通気性や排水性が悪いため根が伸びにくくて、砂や石が多い場合には保水性が良くないので水枯れしやすく、また安定性もありません。成分のバランスがいい土の状態のことを団粒構造(だんりゅうこうぞう)と呼びます。つまり均一でないいくつかの種類の土粒子が小さな塊を作り、さらにそれが何重にも集まって大きな塊となった土壌のことです。粒子や塊の間にできた隙間によって、土壌の保水、排水、通気がよくなります。

植物を育てる条件としては土の性質も大事です。pHで示される水素イオン濃度の測定により、酸性・アルカリ性の程度を調べることができます。これは見た目や感覚ではわかりづらいので、市販の測定器具や検査薬を使って調べましょう。結果が中性であれば植物の生育に問題がないとされますが、実際には弱酸性ぐらいが最適です。もし、調べてみて土がアルカリ性や強い酸性だったとしたら、植物の生育には向いていないことがわかります。調査をする際は、一か所だけでなく複数の場所で、土は表面でなく深さ50cm程度のところから掘り返して行いましょう。
よくガーデニングの入門書などには、最初に苦土石灰を土に漉き込むように書いてあったりします。日本は酸性土壌が多いから、それを中和するために手っ取り早く石灰で中和をということです。でも土の状態を調べずにいきなりこれを行うのは非常に危険です。石灰にはいくつか種類がありますが、強いアルカリ性を持つものがほとんど。土壌がアルカリ性に傾くと、植物の生育に必要な微量要素が水に溶けにくくなり、根からその要素を吸い上げることができなくなれば植物は徐々に弱っていきます。中にはアルカリ性が好き、酸性が好きという植物もいるものの、それは少数派です。土壌をアルカリ性にするのは簡単でも、一旦アルカリ性になった土を中性や弱酸性へ戻すことは容易ではありません。
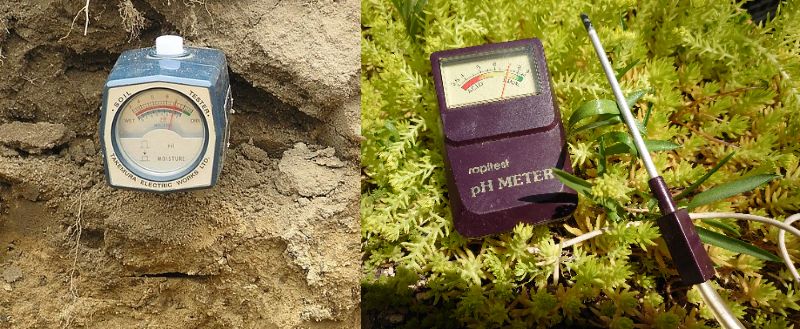
土を植物の栽培に適さない状態から適した状態に改善する方法が土壌改良です。土が団粒構造になっていない場合やpHの値が悪いような場合には、土を掘り返して空気を送り込むことからはじめます。パーライト[1]火山ガラスを加熱し膨張させたものやバーミキュライト[2]ひる石を加熱し膨張させたものといった改良剤を加えると通気性、保水性を上げることが可能です。あるいは黒土や赤玉土などの園芸用土を混ぜ込んでもいいかもしれません。そして水を与えながらしばらく時間をおいて、土が安定したところで植物を育てはじめるといいでしょう。そして酸性が強い場合は、貝殻を原料にした石灰か草木灰を、アルカリ性の場合はピートモス[3]ミズゴケなどが堆積されてできた泥炭で乾燥させた状態で販売や鹿沼土[4]かぬまつち・栃木県鹿沼市辺りで採取される軽石を混ぜてあげることで少しずつ調整していきます。

大事なことは土を最良の状態で維持していくことができるかどうかです。そのためには土の中にいるたくさんの微生物や小動物の役割が欠かせません。「えさ」となる有機物が土の中に混ざることによってそこにいる生物たちが活発に活動を続け、土を耕し植物に必要な養分を作り出します。そして植物が生長して地上の生物との関わりが起こることで新たな「えさ」が発生し、やがて循環が行われるように。この循環が滞ってしまうと、土壌は弱り、植物も元気に育つことができなくなります。良質の肥料を使うことによって、優れた土壌を維持し続けることが大切です。