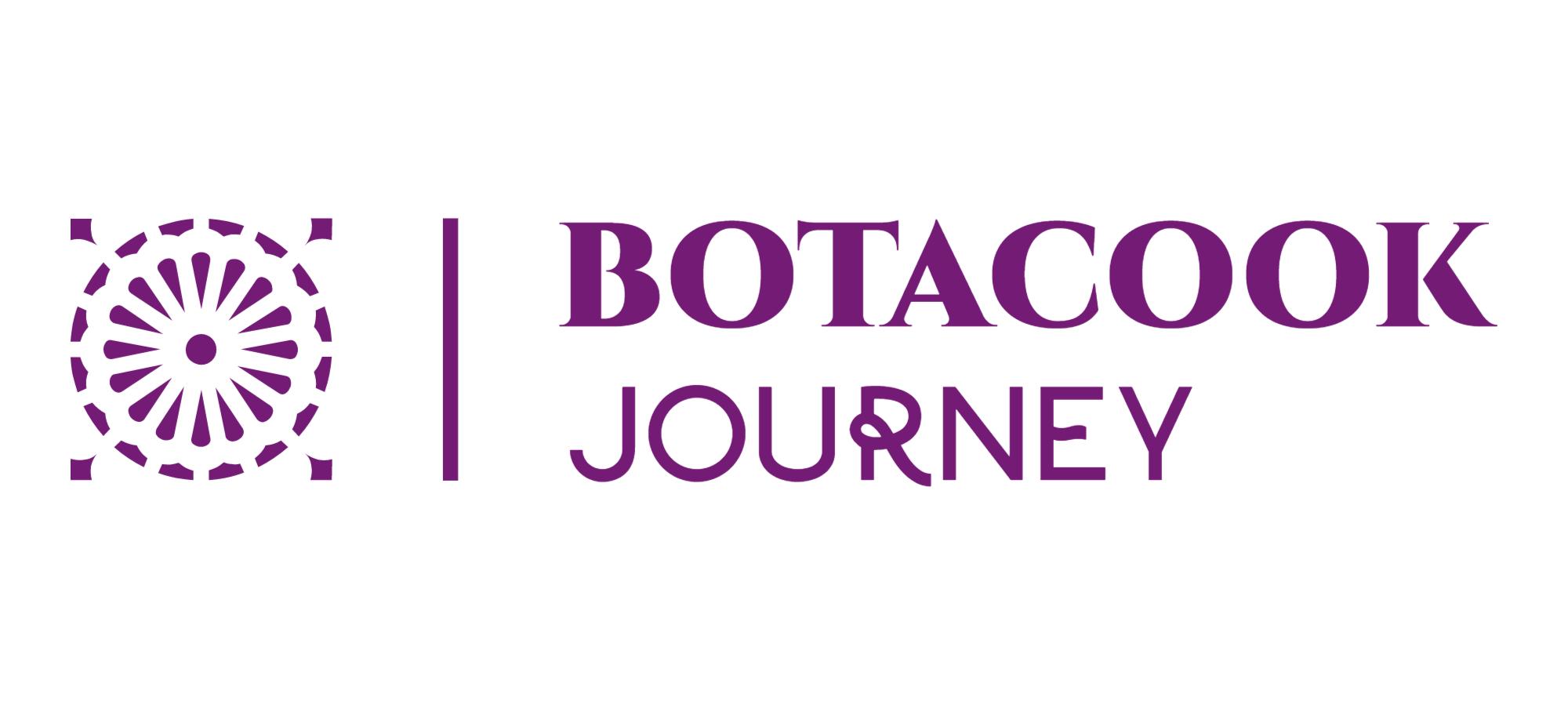庭や花の仕事をする人の中にもいわゆる「斑入りマニア」たちがたくさんいます。斑入りとは、よく見かけるものではホスタ(ギボウシ)、リリオペ(ヤブラン)、ヘデラ(アイビー)、ツルニチニチソウ、観葉植物のデュランタやポトスなどのように、葉の一部の色が薄くなったり白っぽくなったりする種です。その斑入りに魅せられるとついつい集めてしまい、素材として使いたくなります。
ガーデニングといったらやっぱり色とりどりの花に目がいくものです。いかにきれいにたくさんの花を咲かそうかと考えるのではないでしょうか。それでもいろいろ試しているうちに、斑入りの葉の美しさにも、花の彩りとはまた一味違った魅力があるものだとわかるようになるかもしれません。普通は緑のはずの葉に斑が入る植物を利用して、微妙な色や模様の違いとか季節による変化を楽しめるよう、ほかの植物との組み合わせで花壇や寄せ植えを演出してみましょう。

斑が入るという現象は、葉の細胞内にある葉緑素が減少してその他の色素が表面に現れるものです。種類によって葉緑素のすべてが失われるものもありますが、一部だけ失われるもののほうが圧倒的に多くみられます。葉の緑の部分が濃淡になったり、黄色やピンクや白が混じったりするのです。斑の入り方は様々で、全体がまだらになるもの、縞のように入るもの、ふちだけ色が変わるもの、若い葉だけ色が薄いものなどがあります。

斑が現れる原因についてはいくつかのパターンがあり、通常は遺伝子にその情報を持っていて引き継がれるものです。しかし、遺伝しないキメラ斑というものがあります。キメラとは遺伝子の異なる細胞が同居する現象です。三層構造になった葉の中で、葉緑体の発達に必要な遺伝子が変異した層だけ色が抜けます。それ以外にウイルス性の病気によるものもあり、その場合にも遺伝しません。チューリップやグラジオラスなどの花弁に入る模様も同様の病気です。植物が光合成をする際には葉緑素が必要なことに変わりありません。ですから葉緑素の少ない種は光合成の活動も小さくなります。そのため同じ種の中では斑があるものはその生長に限界があると考えられ、栽培にも工夫がいる場合が多いです。もともと斑入りの植物であっても、日照や栄養の条件が悪くなることによって斑が消えていってしまうことがあります。それでも条件が整えばまた斑が復活するかもしれません。斑入り植物と呼ばれるものには、たくさんの種類が存在します。花や実のつく植物やカラーリーフプランツなどとのバランスを考えて、一年草、多年草は花壇のアクセントとして、低木や高木は目立つところにポイントとなるように配置しましょう。それにグランドカバープランツの利用もおすすめです。
斑入り植物は、学名に変種という意味でヴァリエガタvariegataと付記されます。var.と略されることが多いです。

斑は訓読みだとまだらです。英語では植物の斑入りはvariegatedヴァリエゲイテッド。ほかにもまだら模様を意味する単語は豊富にあります。この単語は必ずこれに使うと決まっているわけではないものの、だいたい使い分けをするようです。上記のウイルス病による花のまだら模様はmottleマトル、斑点のある動物はdappleダプル、三毛猫のような模様はcalicoキャリコ、蝶や蛾はirrorateイラレイトという具合。主に鳥にはspeckledスペックルドかpiedパイドが付くことが多いです。ちなみにシャーロック・ホームズが登場するコナン・ドイルの小説「まだらの紐」[1]1892年初出の原題はThe Speckled Bandで、紐や帯のバンドと楽団のバンドをかけています。また、グリム童話の「ハーメルンの笛吹き男」の英題はPied Piper of Hameln「ハーメルンのまだら模様の服を着た笛吹き男」ですが、ドイツ語の原題はRattenfänger von Hameln「ハーメルンのネズミ捕り」です。ちなみに、現在では英語でpied piperというと、元の意から派生して「言葉巧みに誘惑する人」とか「無責任な約束をする人」という意味で使われます。

References
| ↑1 | 1892年初出 |
|---|