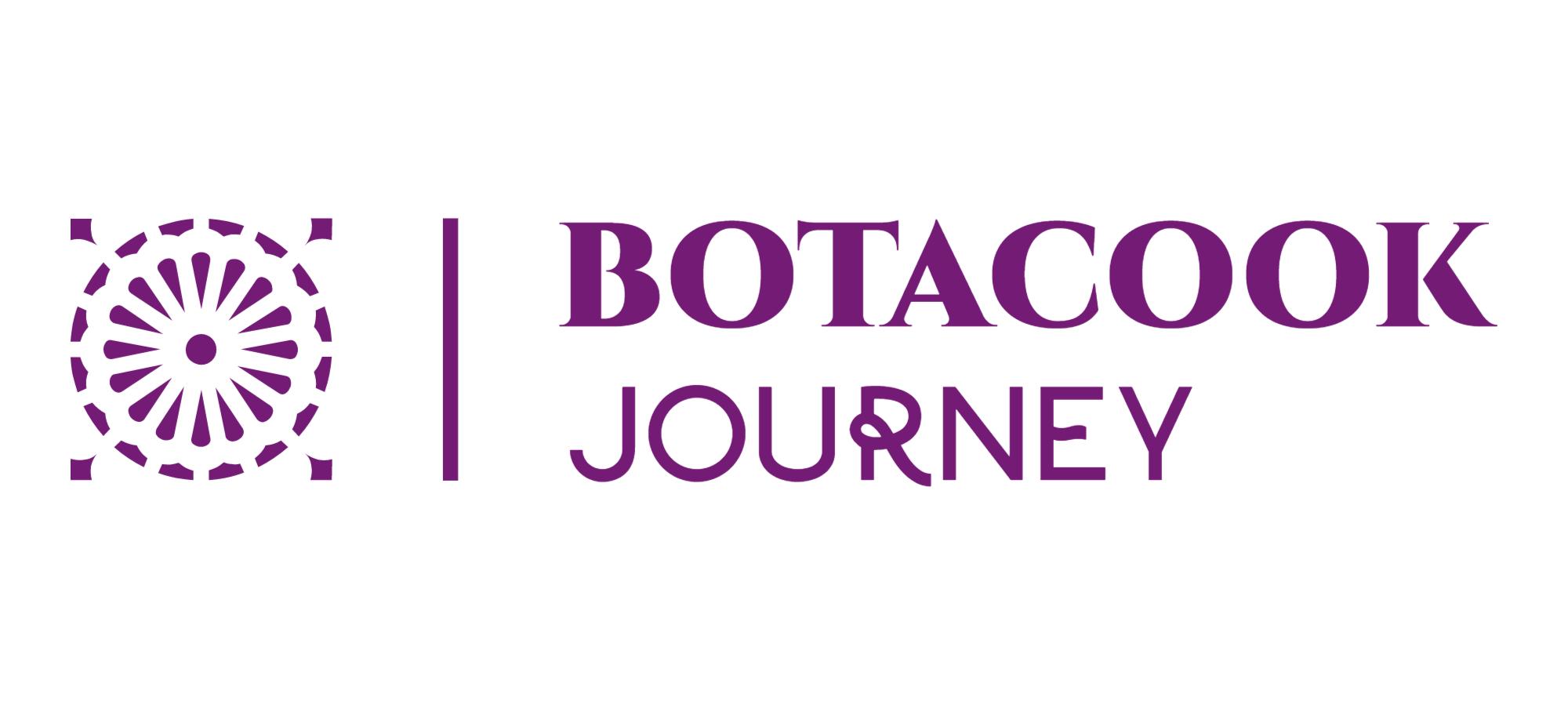オランダのサッカー史上で最高のスーパースターといえばヨハン・クライフJohan Cruijffでしょう。サッカー界では、数々の記録で彼を上回る選手はたくさんいるとしても、その英雄としての地位は揺るがないでしょう。彼が好んでつけた背番号14[1]サッカーでは珍しく、所属したアヤックスでは永久欠番になっていますとともに語り継がれることと思います。
クライフはアヤックス・アムステルダムからFCバルセロナへ移籍した1973年に、アトレチコ・マドリードとの試合で伝説のゴールを生み出しました。右からの速いクロスに合わせて走り込み、ゴール前でジャンプしながら踵で蹴りこむというアクロバチックな芸当をやってのけたのです。このゴールによって彼は名声を確固たるものにし、Flying Dutchmanフライング・ダッチマンと称されることになりました。日本ではこのフライング・ダッチマンをそのまま「空飛ぶオランダ人」と訳していますが、それはただ単にヨーロッパ文化に理解がなかったからに過ぎません。実際はその名前だと、本来の意図とは少なからず違ってしまいます。
そもそもイギリスにはFlying Dutchmanという喜望峰付近に現れる幽霊船の伝説があり、それをもとにしたハインリッヒ・ハイネ[2]19世紀ドイツの詩人の著作からリヒャルト・ワーグナーがオペラ”Der Fliegende Holländer”(英題:”Flying Dutchman”、邦題:「さまよえるオランダ人」)に仕立てました。このオペラは、1843年にドレスデンのゼンパー・オーパー[3]当時のザクセン王国の国立歌劇場 ワグナーが指揮者を務めたで初演されてから、現在まで世界中の歌劇場で上演されています。そのため、フライング・ダッチマンという言葉は欧米ではよく知られているのです。つまりフライング・ダッチマンとは遭難して海に消え、霧の中から突然に現れては消えるオランダの幽霊船のこと。7つの海を永遠に航海していると言われます。ですからクライフの異名は、物理的に空を飛んでいるように見えるとかではありません。抜群のスピードとテクニックでピッチを縦横無尽に駆け回り、突然ゴール前に現れたり、有名な「クライフターン」でディフェンダーを置き去りにしたりという神出鬼没なプレーが幽霊船をイメージさせたために付けられたのです。そうは言っても、クライフのことを「さまよえるオランダ人」と呼んでピンとくる人がどれほどいるのかという疑問もあります。
クライフ以外にも、様々なスポーツで「フライング・ダッチマン」の異名をとる選手はいます。それは上述のようなイメージから付けられるものなので、オランダ人に限ったことではありません。


クライフがオランダ代表として出場したFIFAワールドカップ本大会は、第10回1974年の西ドイツ大会のみです。二次リーグのアルゼンチン戦[4]4-0で勝利では飛び出してきたキーパーをワンステップで躱してゴール。続くブラジル戦[5]2-0で勝利では、左からの低いクロスにオフサイドぎりぎりのタイミングで飛び込み、またもやジャンプしながらボレーシュートを決めます。オランダは破竹の勢いで決勝まで進んだものの、開催国で「皇帝」フランツ・ベッケンバウアー、「爆撃機」ゲルト・ミュラー、「ジプシー」ヴォルフガング・オヴェラートはじめ全員がスター選手ともいえる西ドイツに敗れました。しかし、この大会でのオランダ代表の、ポジションにこだわらず全員攻撃・全員守備を繰り広げる通称「トータルフットボール」は、クライフの活躍とともに人々に記憶されています。
ちなみに、この頃の日本では現在とは大違いでサッカーは末梢的な扱い。サッカー世界一を決めるワールドカップといえどもテレビでの放映はほとんどなく、決勝戦だけが生放送[6]当時の東京12チャンネルでした。夜中に起きてそれこそテレビに嚙り付いて観ていたことを思い出します。

あまり有名ではありませんが、実はフライングダッチマンというカクテルがあります。私の知る限り[7]同じ名前でレシピは多々あります、イェネーフェルというオランダ産のジンを3オンス、オランダ製のホワイトキュラソーをバースプーン1杯、オレンジビターズを1ふりしてシェイクするものです。